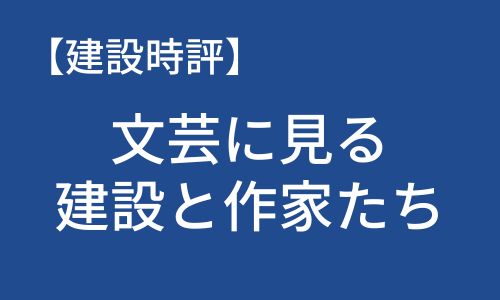
土木の授業で,幾つかの分野の講読を義務付けて,レポートを提出させたことがある。その分野の一つが,建設工事の現場を舞台にした文芸作品である。
建設の世界の我々は,作家が我々の世界に向けた関心の的を捉えて自らを振りかえり,己の矜持を確かめたい。そのような意図で,学生たちを指導していたのである。
* * *
そうした作品をものした作家たちとその作品を,順不同で挙げてみよう。
往時,作家たちの大御所的な存在だった幸田露伴の作品に「五重塔」がある。主人公は腕は達者だが頑固一徹の故に,仲間からも敬遠されていた大工。その職人凱歌を謳った。
菊池寛の「恩讐の彼方に」は,殺人を犯した男が,逃亡流浪の末に九州の耶馬渓で,鑿と金槌をふるって単身,貫通させたトンネル工事の物語。主人公を追ってきた敵討ちの男が,主人公とともにこの難業に挑み,遂には敵討ちの努めを放棄してしまう顛末を描く。
ともに文学史上に残る名作で,往時には戯曲化されて新派などの舞台で演じられて,人気を集める演目だったそうだ。
そのほか,名だたる作家の作品がある。
三島由紀夫は,一見,土木屋風情とは縁遠い印象があるが,奥只見のダム現場を舞台にした「沈める滝」がある。主人公は現場の土木屋だが,土木工事が主題ではなく,工事現場を舞台に,男女のしがらみを描いた。
松本清張の「天保図録」は,天保改革に取り組む幕閣の水野忠邦とその用人の鳥居耀蔵が主役。鳥居耀蔵が印旛沼や多賀沼の干拓工事の,泥濘にまみれた現場に登場する。
石川達三には,ダム工事を舞台にした2作品がある。その一つは,多摩川の源流の水没する小河内村を舞台にした「日陰の村」。事業を推進する役所と,これに反対する近隣の住民と,介入する政治家たちに翻弄された挙句に,土地も財産も失って,身一つで水没する村を出て行った地元住民たちの悲惨な姿を描いている。もう一つは,北陸の九頭竜川ダム工事を描いた「金環食」。この建設事業を巡る政治家たちと業者の生態が実に生々しい。
意外なことに女流作家に,工事現場や現場技術者を描いた作品が眼につく。
曽野綾子は「無銘碑」で,赴任した外国の道路工事現場で非命に倒れた土木屋を描いた。執筆中に接した土木屋の矜持に感銘を受けたと語っている。もう一つはダム工事を描いた「湖水誕生」。水没の運命にある桜の木を移植して救済したエピソードを取り上げた。
杉本苑子にも,土木の現場を舞台にした2作品がある。その一つは,多摩川から江戸まで,上水用の水路工事を描いた「玉川兄弟」。作者が創作した請負の実態は,土木屋から見ても説得力がある。もう一つは,濃尾平野を流れる木曾三川の堤防工事の「孤舟の岸」。幕府の役人の無理難題を飲まされた末に膨大な赤字を背負い込み,竣工後に藩政への申し訳のために自裁して果てた薩摩藩士の生き様を描く。慰霊碑が現地に残っているそうだ。
同じ工事をテーマにして,村木嵐が「頂上至極」を書いている。
芝木好子の「女の橋」は,現場の土木屋が主人公の恋愛小説。女流作家の作品には,現場の土木屋に女性が絡む場面が多い。現場の土木屋は,そんなにモテるのだろうか。
新田次郎は,「富士山頂」で富士山の頂きに世界最大の気象レーダー基地を建築する工事を描いた。次いで,景勝地の霧ヶ峰を舞台にした道路工事の「霧の子孫たち」がある。取り上げた環境破壊に先進性がある。さらに,北海道開拓時代の道路工事で辛酸をなめた囚人たちを描いた「赤い人」がある。
吉村昭は,綿密な調査に裏付けられた記録文学のジャンルを生み出した。トンネル工事を取り上げた2作品がある。その一つ,黒部川発電所建設に関わるトンネル工事を描いた。「高熱隧道」では,岩面から噴き出す高温の蒸気や,冬季に建物ごと飛ばされて全員が死亡する泡雪崩など,凄まじい場面が展開する。もう一つの「闇を裂く道」では,多くの犠牲者を出した難工事の東海道本線の丹那トンネルの工事を描いた。西口から掘り進んだ鹿島組は今も業界に君臨するが,東口から掘進した菅原組は今はない。長子が土木屋はごめん被ると,父親の後を継がないで,廃業してしまったのだ。
安部譲二は,「囚人道路」で,北海道開拓時代に道路工事の重労働を強いられた囚人たちの悲惨な姿を描いた。彼は創作活動に入る前に,獄舎につながれたことがあったそうだ。ご当人の体験の記憶が,この作品に映し出されているのだろうか。
小池嘉孝が「常紋トンネル」で取り上げたのも,北海道のトンネル工事である。
三田英彬は,津軽海峡を海底で結ぶ「青函隧道」をノンフィクションタッチで書いた。
北海道出身の渡辺淳一による「峰の記憶」は,北海道の原野の道路建設現場を舞台にしたフィクション。環境問題を取り上げた先進性がある。実在の建設工事と錯覚した地元民が問い合わせたほどのリアリティーがある。
城山三郎の「黄金峡」は,福島県の山奥のダム建設に直面して欲の皮が突っ張った地元住民たちが,補償交渉の場で海千山千の輩に翻弄された挙句,生活も心も壊されていく生態を冷徹に描いている。
木本正次の「黒部の太陽」は,大ヒットした映画の原作。原作はルポルタージュ風に淡々と書かれている。映画では,現場の土木屋は,娘が入院しても仕事を優先して見舞いにも行かない,臨終の場にも行かない非人道的な姿が美談として描かれる。この虚構に,観客は深い感銘を受けたのだが…。
タカクラ・テルが,江戸時代に富士山麓の不毛の地に,箱根の芦ノ湖から農業用水を引いた「箱根用水」を描いた。彼はこの用水事業を世に知らしめようと,長年,運動してきた地方政治家である。
九州出身の帚木蓬生が描いた「水神」は,郷里の筑紫川から台地の上の農地に,個人の力で農業用水を引く工事を担って,地元民の宿願を実現させた江戸時代の物語である。
今西祐行の「肥後の石橋」は,今も熊本県下に点在する石造橋梁の工事を描いた。
「戦場にかける橋」の著者は,フランス人のピエール・プール。映画化されてアメリカでアカデミー賞を取り,日本でもヒットした。
* * *
こうして挙げてみると,土木が主題の作品が圧倒的に多い。何故に土木が多いのか。
作家たちが現場の土木屋に向ける視線は,同情と憐憫,感嘆と称賛で共通している。同情と憐憫は,特に請負現場の土木屋の置かれた環境と境遇にある。
3K(危険,汚い,きつい)に加え,片務性の濃い請負条件,慢性的な買い手市場,官尊民卑などと揶揄される風潮がある。請負側の土木屋は,カスハラ(カスタマーズ・ハラスメント:顧客や施主による嫌がらせ行為)が認識されない昔から,カスハラ的なプレッシャーを忍従していた。
こうした環境にも関わらず,彼らが保つ矜持に,作家たちは感嘆と称賛を送った。そして,発注者から強いられる無理難題に応え,一徹な職人を巧みにあしらって数多の困難を克服してきた。その姿に,作家をして「土木は神」と言わしめる。偶々,敬虔なカトリック信者の作家が,現場の土木屋に神の姿を見出したのであろうか。
だが,それで良いのか。
土木屋の中には,官庁,業者,大学院でキャリアを積んだお歴々が,高級官僚,経営者,教授へと登りつめるのだが,作家たちが同情,憐憫,感嘆,称賛を贈るのは,こうしたお歴々ではない。それは,栄誉栄達とは無縁の,請負側の現場土木屋なのだ。お歴々が「俺も土木屋だ」とばかりに感嘆や賞賛に便乗して悦に入るのは的外れなのである。
* * *
作家の食指が建築よりも土木に向けられる理由は,土木のほうがはるかに,同情,憐憫の描写に適う環境にあるからだと思う。こうした筆致の作品が存在感を示すこと自体,請負側の現場土木屋の社会的ステイタスが,旧態依然であると考えてよさそうである。作家たちからの同情,憐憫は褒められたことではない。それでは良くないのである。
土木のお歴々は,持てる権能を駆使して,土木の世界の人々たちのステイタス向上に努めて貰いたい。
『土木は神』の賛辞は,実はオブラートに包んだ告発と考えたいのである。
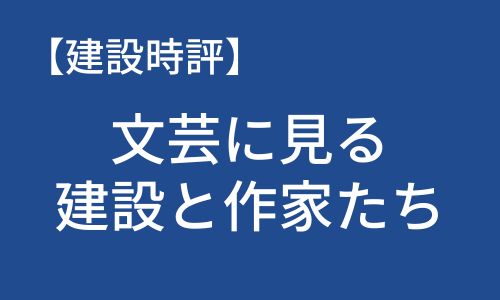
おすすめ書籍・サービス