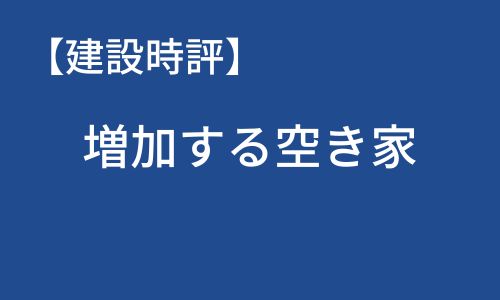
総務省が5年毎に行う住宅・土地統計調査の、令和5年度調査の速報集計結果が発表になった。日本の総住宅数は6,502万戸で過去最多で、前回調査から4.2% 261万戸増加した。5年間の人口、世帯数の変化を見ると、人口は229万人減少し、世帯数は226万世帯増加した。人口が減少する一方で世帯数が増加するねじれ現象は人口動態が過渡期にあることを示すが、世帯数の増加を上回る住宅数の増加は、空き家増に直結する。
空き家数は900万戸で過去最高となった。5年間で51万戸増加し、空き家率は13.6% から13.8% になった。内訳では賃貸用の空き家が最も多いことは変わらないが、割合は初めて50%を下回り、一般の住宅の37万戸増が目立つ。
かねて空き家の多さは社会課題であり、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)(2015年)が規律され、対策が進められてきた。特定空家に対する措置が同法の目玉で、認定した特定空家に、除却、修繕、立木竹の伐採等の指導、勧告、命令ができ、埒があかない場合は、行政代執行によって強制的に解体する。令和5年3月調査では、行政代執行で解体された特定空家は180件で、所有者が特定できない場合の略式代執行を含めても600件弱に留まる。増加する空き家を解消する効果的な方法にはなっていない。最終の解決方法として準備するが滅多に適用しないという意味では“伝家の宝刀” で、公共用地取得の際の土地収用と同段といえる。
行政代執行による特定空家除却には他の問題もある。まず、特定空家の認定にいたる時間と人的コストの多さだ。市町村内に相当数の職員のほか、弁護士、建築士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、宅地建物取引士、生活者代表、学識経験者などで構成する委員会を立ち上げ、一つの空き家を特定空家と認定するまでに数回の委員会を開く。この間も職員は所有者の意向調査、空き家の現状把握を続け、所有者が遠方の場合は出張もいとわない。専門家の能力と時間を浪費し、行政の費用が嵩張る。
次に、解体費の回収だ。市町村が立て替えた工事費を所有者から回収することは必ずしも容易ではない。所有者が支払わない、支払えない場合は、解体費不払いを理由とする差押え等を行う。市町村長は租税に次ぐ先取特権を有するが、担保権には劣後する。土地が売れない、売れても解体費に届かない場合は、実質的に市町村が負担する“公費解体” になる。公費解体は被災者の生活再建を支援する場合でも制限が多い。放置しておけば、自らの不作為を公費で解消してくれると思わせかねず、モラルハザードが危惧される。
“焼け石に水” の空家特措法が改正された(2023年)。改正法の眼目の一つは、管理不全空家を規定し、放置すれば特定空家になるおそれのある管理不全の状態で、市町村長による指導、勧告を認める。より早い段階から公的に関与する仕組みである。管理不全空家には、住宅用地の固定資産税の特例(200㎡迄1/6、200㎡超1/3)を認めないことも新設した。空き家といえども居住用の建物があれば土地の固定資産税が安くなる特例が、利用目的がない場合でも解体せず、放置につながるとの指摘に対応した。
他の一つは、空家等管理活用支援法人を規定したことである。解体による状況の改善にも、売買や賃貸による不動産流通化にも、立ちすくんで動けない所有者の啓発や相談によって意思決定を促し、利活用につなげる目的がある。意思決定に必要な情報を提供するほか、ニーズに合わせた相談ができるよう、司法書士、税理士、土地家屋調査士、建築士、宅建士などで構成することが想定されている。
空き家が放置されるケースとして、複数相続人で相続したものの遺産分割協議が整わず、共有するところ、共有物の処分に必要な全員合意が得られない状況がある。空家等管理活用支援法人では、このような“しこった” 状態の空き家について、利活用に向けた障害を取り除き、流通可能な不動産に“商品化” する。その後、宅地建物取引業者が媒介して売却や賃貸につなげる。
空き家の流通が進まない理由の一つとして、空き家は一般に低廉で、売買や貸借の媒介手数料が安いことがあるとして、国土交通省は宅地建物取引業法が規定する媒介手数料の例外規定を設けた。改正後は売買代金800万円までは30万円の1.1倍を受領することができる。賃貸については従来の賃料の1.1ヶ月分が原則のところ、2.2ヶ月に倍増した。宅地建物取引業者が空き家の媒介ビジネスに魅力を感じることを通じて、空き家の市場流通を促進する狙いがある。
SDGs は目標12に、つくる責任・つかう責任を掲げている。既存建築ストックを活用することは新築することと比べて二酸化炭素排出量が少ないと考えられることから、国の位置付けは空き家についても、第一義は利活用である。半面、全ての空き家の再生利用が現実的かと問えば、答えは否である。今後は世帯数も減少し、空き家が益々増加することを考えれば自明である。現実的には解体が重要な選択肢だが、これまでのところ、解体の方法論が積極的に論じられてはいない。
空き家の解消に向けて建設分野に期待される貢献は、新設の空家等管理活用支援法人に参画することはもとより、状況把握のための建物診断、利活用のためのリノベーションを担うことであり、今後主題となる建物解体に技術革新をもたらすことである。建設分野にとって必ずしもビジネス上の魅力に富むわけではないが、外部不経済をもたらす空き家を放置することは地域価値を貶め、地域の持続可能性をゆるがせにする。地域を創る産業として看過することなく取り組むべき課題である。
「解体費用が高いから」が空き家を放置する理由の第二位に挙げられている。実際に高いと考えているケースのほか、適正な解体費がわからない、示された額が適切かわからないケースも少なくないであろう。合理的な解体費を社会的に共有することが求められ、“持続可能社会の解体工事” のあり方を示すことも期待される。廃材の利用も考える必要があろう。チップにしてバイオマス発電に使う、仮設、外構や補助構造材に使う等、量的にとらえることで見える可能性もある。
建設産業は新築工事の分野で信頼を得ている半面、リフォーム工事では建設業の免許が必要ない事業者を中心に不適切な工事や高い工事費を巡るトラブルがあり、信頼産業と認められるに至っていない。第三者認証制度を創設するなど、新たな発想も期待される。建築士に対する社会の役割期待は、“造ったあとの価値を創るひと” へと拡大しつつある。
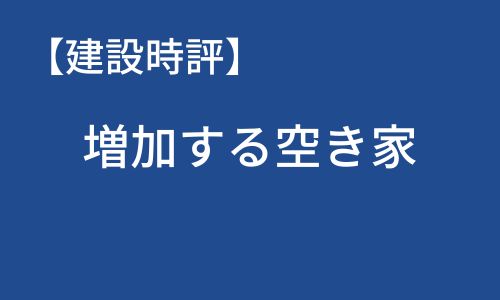
おすすめ書籍・サービス