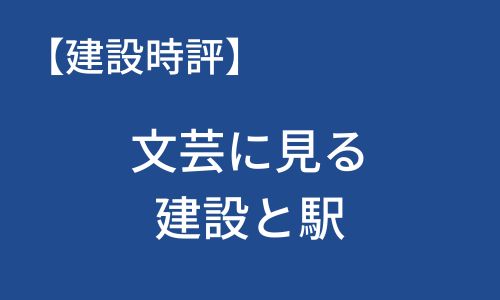
日本全国に張り巡らされた鉄道網の中心にある駅は東京駅である。東京駅には0㌔標識が置かれ、東京駅を目指す列車は上り、東京駅から出ていく列車は下りと称される。東京駅を語る数多の文献のなかから、小野田滋「高架鉄道と東京駅[上][下]」(交通新聞社新書)を引いて、建設の経緯と顛末を描く。
“1900年当時、東京に集まる線路の終着駅は、新橋や上野などの頭端式(行きどまりとなって折り返す形態) の駅だった。”
“上野と新橋とは距離があるので、この区間を鉄道で結べば便利であるとの意見が、早い段階から出されていた。”
“在日していたお雇い外国人のドイツ人鉄道技師のフランツ・バルツァーは、ヨーロッパの大都会に多い頭端式駅には発展が見込めないとして、日本では通過式の中央駅を設けるべきであると論じ、幕閣や政府要人に働きかけていた。” 一旦は新橋と上野を結ぶ地上線路が構想されたが、道路交通が阻害されるとして地元の猛反対にあい着手できなかった。
“1884(明治17)年、都市計画案「東京の市区改正意見書」が提案された。このなかに、上野―新橋間の高架による鉄道敷設と、皇居の東に新しく、東京の中心となる駅を設置するという計画が含まれていた。東京の中心となる駅は、中央停車場と名付けられ、これが現在の東京駅ということになる。”
“中央停車場の用地には、三菱が原と俗称される土地が提案された。ここは、もともとは大きな大名屋敷が立ち並ぶ江戸の中心地だった。明治維新の後、地方の大名がすべて国もとに引揚げて空き家になっていたところ、火事にあって焼失し、その焼け野原を陸軍が練兵場として使用していたが、政府の意向で三菱の岩崎弥之助に払い下げられた。”
“手つかずになっていたこの土地に中央停車場案が出された結果、現在の地に駅の建設が決まったのである。”
“フランツ・バルツァーは日本文化を敬愛し、和風様式を取り入れた中央停車場を設計した。だが、政府要人たちには不評だった。”
“辰野は、バルツァーが設計した外観を「西洋婦人が洋服を着ていながら、赤毛の島田髷に花簪をさし、カラやカフスの代わりに友禅の布を巻き付けて、駒下駄を穿いたという扮装」と述べ、自分自身は珍しいから嬉しいだろうが「日本人の目には甚だ不格好で不釣り合い」、どうしても「島田髷の洋美人式」になってしまうと酷評した。”
“1903(明治36)年、中央停車場の設計が辰野金吾博士に依頼された。辰野は「丈が低くても、色が黒くても、洋服を着るならボンネットをかぶり、靴を履く方が適当である」と、洋式の建築様式を選んだ理由を説明した。”
“西欧様式の中央停車場を設計した辰野は、当初は当時最新の工法である鉄骨鉄筋コンクリート構造を予定していたようだが、新しい技術を信用できなかったのか、各所にコンクリートを用いつつも、基本設計を鉄骨煉瓦造りに変更した。”
浜松町から丸の内まで、高架鉄道が建設された。名付けて新永間高架鉄道。“新永とは、浜松町にあった新銭座と丸の内の町名である永楽町の頭文字を採った名称である”。
“この高架鉄道を請け負ったのは、杉井和一郎、大倉粂馬、鹿島岩蔵、杉井浅次郎で、中央停車場の基礎工事を杉井浅次郎、本屋工事を大林芳五郎、烏森(新橋)停車場の上屋工事を清水満之助が請け負った。すべて個人名であるが、大倉粂馬は大倉土木で現在の大成建設、鹿島岩蔵は鹿島組で現在の鹿島建設、大林芳五郎は大林組、清水満之助は清水組で現在の清水建設を代表する人物だった。”
“杉井和一郎と杉井浅次郎はともに杉井組の人物だが、杉井組はその後、社業が傾き解散してしまった。”大林芳五郎率いる大林組が“中央停車場の駅本屋を完成したのは、1913(大正2)年3月。翌年にはプラットホームも完成。延べ74万人の職人、6年の歳月をかけて作られた中央停車場は1914(大正3)年12月18日に開業式典が催された。”
“このとき中央停車場の駅名が東京駅と定められた。完成した東京駅は、東海道本線の起点となり、長さ445㍍、高さ46.6㍍、4面のホームに8本の発着線を設ける世界的にも例のない巨大な建物だった。”
“東京駅の中央玄関は、実は皇室専用の出入口であり、宮廷・貴賓専用通路、皇室専用の休憩所なども用意されていた。その立地から、東京駅は天皇家を迎える場として建てられていたのである。”
“東京駅周辺の茫漠たる広大な空き地を、土地の所有者だった三菱が計画的に開発し、短期間で日本を代表するビジネス街へと変えていった。” “ 丸の内の繁栄に東京駅が果たした役割は大きく、東京駅は日本経済の発展の起爆剤になった。”
1923(大正12)年9月1日、午前11時58分、関東大震災が発生した。
“鉄道関係も被害は大きく、関東の路線は全て不通となり、多くの駅舎が焼失した。車両被害も大きく、機関車108両、客車486両、貨車1272両が失われた。この時、東京駅はほとんど無傷だった。プラットホームの一部が倒壊したが、1名の死者も出さず、技術の優秀さを証明した。周囲は全て火災被害を受け、東京駅には多くの避難者が集まることになった。広間や待合室、通路にいたるまで、押し寄せた人々で埋め尽くされた。”
“2日後に山手線が運転再開。東京駅は9月21日に営業再開、10月末には東京周辺の鉄道はおおむね復旧した。その復旧の速さは、鉄道マンたちの日頃の研鑽の賜物だった。”
“第二次世界大戦に突入し敗色が濃くなると、1944(昭和19)年末頃から空襲が激しくなった。1945(昭和20)年5月24・25日には、東京駅にも爆弾・焼夷弾が複数命中して、駅本屋の3階部分、第1ホームのすべて、第2ホームのほとんど、第3ホームの事務室と待合室、第4ホームの一部、信号扱所が消失し、東京駅を印象づける南北の円形ドームの屋根も破壊されてしまった。”
“駅員たちの不眠不休の復旧作業で、27日には5本の列車を運転させ、6月2日には通常運転にこぎつけた。”
“戦争が終結して日本が再生の道を歩もうとしたとき、日本の鉄道網はその能力を大幅に減退させていた。”
“再建された東京駅は、戦時中は軍需輸送の拠点に、戦後は一転して復員兵士の帰郷や疎開先からの移動、生活物資の買い出しのために、機能することになった。”
“消失した3階部分は、時間も資材もないので完全な復旧はあきらめ、2階建てでの再建となった。再建は1947(昭和22)年までかかり、シンボリックな存在だったドーム型の屋根は直線的な形状での再出発となった。”
1949(昭和24)年、日本国有鉄道が発足し、鉄道事業は次のステップを踏み出した。
“1954(昭和29)年10月14日に八重洲口新駅舎が竣工した。地下2階、地上6階のモダンな美しいビルで、上階には百貨店、名店街には有名老舗が入り、大衆的で娯楽性のあるイメージが東京駅に付加されたと言える。”
“1964(昭和39)年には東海道新幹線が開通。1987(昭和62)年に分割民営化により国鉄はJR 各社に分割されて現在に至っている。”
“2007(平成19)年6月、丸の内駅舎保存復原工事が着工された。創建時の姿に復原可能なものは限りなく復原する工事だった。工期は5年4か月、工事費は約500億円。駅の機能を停止させずにやってのける大プロジェクトを鹿島・清水・鉄建JV が担った。”
“空襲後に仮の八角屋根だったはずが60余年間も東京駅の姿として象徴となって来た屋根が、2009(平成21)年7月に外された。”
“2012(平成24)年10月、東京駅は100年の時空を飛び越えて、辰野金吾が設計した創建当時の姿に復原されて登場した。
”東京駅は、あらためて首都・東京の顔として、生まれ変わっていくのである。
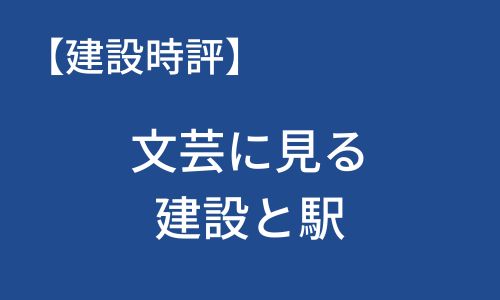
おすすめ書籍・サービス