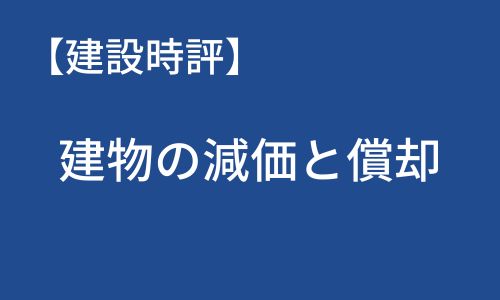
建物が持つ性能は一般に新築時が高く、時間の経過や使用による損耗によって低下する。性能の低下にともなって減価が発生することに特段の違和感はない。
性能や額が徐々に減少することを償却といい、償却が進んでやがて使用できなくなる資産を広く償却資産という。この点で建物は償却資産である。
償却と減価に関連する制度に減価償却制度がある。減価償却は、償却資産の取得のために出捐した費用を耐用年数にわたって期間配分する会計制度である。減価償却制度がなければ、費用を出捐した年、新築建物でいえば竣工して請負代金(イニシャルコスト)を支払った年は大幅な出金超過、つまり赤字になる一方、運用期間中は維持管理費(ランニングコスト)が費用となる。減価償却制度によって、入手に要した費用(イニシャルコスト)のうち当該年度に配分された額が費用として認められて黒字が圧縮され、場合によっては赤字となることにより、収益税(個人の所得税、法人の法人税)の節税効果がある。この効果は耐用年数にわたって認められるから、減価償却制度の節税効果は継続的に享受できる。
減価償却費は誰に支払う(キャッシュアウトする)わけでもないのに、非課税で手元に残しておくことができる。何に使っても構わないボーナスと勘違いしがちだが、制度の趣旨は異なる。減価償却費を貯め置けば、耐用年数が到来した時点で再建築に必要な金額が積み上がっているから、それを再建築費用に充て、無借金で新築建物を入手できるとする、企業・事業継続の原則“Going Concern” にある。減価償却は企業経営・事業経営を継続するための仕組みである。
この際、企業毎に償却期間が異なると、保有する資産の価値評価、さらには、企業価値の評価が安定しない。また、税額も異なることから、税務の分野では統一された耐用年数を利用する。これを一般に、法定耐用年数という。
工場の生産機械なども償却資産として償却の対象となる。企業は、節税効果に加えて、技術革新による機械の陳腐化に備える、言い換えると、早期に買い替えて生産性を高め、市場の競争に勝ち抜く必要があることから、早期に償却したい。つまり、企業戦略上、償却期間は短いほうが好ましい。償却期間が短いと1年分の償却額は多額になり、節税効果も大きくなる。変化が早く激しく、競合も厳しくなる社会では、償却期間を短くすることにインセンティブが働く。法定耐用年数の見直しのほか、政策目的に応じて割増償却が認められることもある。
建物と減価償却の関係は複層的である。上記のように早期に償却して新たに高性能の建物を入手することに一定の合理性はある一方、持続可能な社会を実現する観点から、利用できるものはなるだけ長く利用することが要請されている。新築工事は、森林等の資源を多用する、運搬や建設に機器を多用するなど、地球環境に負荷をかける。
建物を木製にして建築物内に二酸化炭素を固定する試みはカーボンニュートラルに貢献するが、既存建築物を大切に継続使用することも重要である。スケルトンは長期に、インフィルは時代の要請に応じて可変的に利用することが落としどころのようだ。
経済社会が変容の速度を速めていること、言い換えると、建物の利用方法が短期に変わる可能性が高まっていることも拍車をかける。当初とは異なる用法に対応することが求められるたびに建替えていては持続可能社会の理念に反し、そもそも投資採算も得られまい。早期に償却して新時代に対応したい企業会計の減価償却と、長期利用しつつ新時代に対応するべき建物の違いを認識し、会計処理上の必要性から生まれる法定耐用年数(画一性)と、経済社会の必要から生まれる長期耐用年数(個別性)の違いを明確に認識するときを迎えている。
日本は土地建物がそれぞれ独立した不動産であることに対し、英米法では建物に独立の所有権はなく土地所有権に含まれる。建物の長期利用を実現する点も英米共通だが、英国と米国では減価償却の考え方が異なる。その対比が興味深い。
英国では建物は減価償却しない。絵画や骨董品と同様、経年によって価値が上昇すると考えるからである。古い建物の希少価値が広く共有されていて、14、15世紀に建てられた木造建築物が現役で使われる。そのような建物の所有者になって趣味や余生の場とすることへのあこがれと、その実現のために行う控えめな追加投資が“償却することのない” 価値を生み出している。
米国ではサブプライムローンの反省から、住宅の銀行融資に際しては、銀行に属さない不動産鑑定士の鑑定評価をとり、その額まで融資する。オーバーローンが破綻につながった経験に基づく仕組みだが、評価では、“改修工事の若返り効果” を重視する。50年経過していても維持管理の状態がよければ、実質経過年数20年などとして価格評価する。若返り効果は何度でも認められるから、“いつまでも残存耐用年数が短くならない” 長寿効果を生む。
減価償却が密接に関係するのは賃貸住宅(事業用の建物)であるが、経過年数に関わらず、購入時点から27.5年の減価償却が可能である。賃貸住宅においても“いつまでも残存耐用年数が短くならない” 制度になっており、古い建物でも償却メリットを享受し続けることができる。住宅価格を構成する土地部分と建物部分のうち建物部分の価格割合が高いことも償却メリットを大きくしている。
英国では“償却せず減価しない” 点に特徴があり、米国は“償却を繰り返して減価しない” 点に特徴がある。これに対して日本の住宅価格は、“償却” と“減価” が不可分で、経年=償却=減価である。木造建築物の税務上の法定耐用年数が22年と短く、22年以上経過した中古住宅購入する場合、償却年数は4年に過ぎない。
“あと何年使えるか” は既存建物を購入する際の価格に決定的に影響する。あと10年しか使えない建物の価格と30年使える建物の価格を比較すると、言うまでもなく、30年住宅の価値が高い。“償却” して“減価” する日本の発想は、建物の経過年数重視の価値基準である。これに対して英米は、“償却” して“減価” することは承知の上でそれを凌駕する方策を見出して持続可能社会に近づけている。
英米のように残存年数を重視すると価値基準は大きく変容する。自用の住宅には幸か不幸か、事業用資産に適用する減価償却制度は適用されない。節税効果とは無縁なことから、耐用年数を延ばすことにデメリットはない。むしろ、1年分のコストを安くするメリットがある。
英国では産業革命後の住宅不足を補う方法として19世紀後半から99年のリースホールドで住宅を賃貸(多額の権利金を取るので実質は売買)するようになったが、その理論的背景は、99年の価値は永久の価値(完全所有権)の価値の99%あることであった。この考えによれば60年の価値は永久の価値の95%である。言い換えると、“あと60年使える” こと証明し、誰もが承知できる仕組みを作れば、それに相当する価格、つまり、永久の95%の価値の存在を社会で共有できる。
持続可能社会に近づけるために、償却と減価の今日的な意味を再確認し、両者の不可分性を断つ仕組みを提示することが求められる。
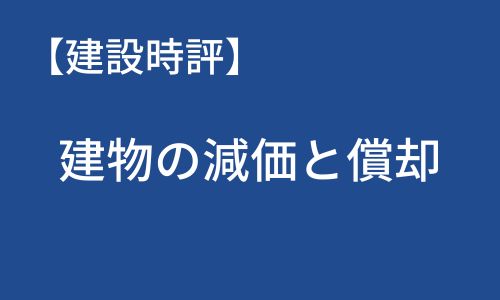
おすすめ書籍・サービス