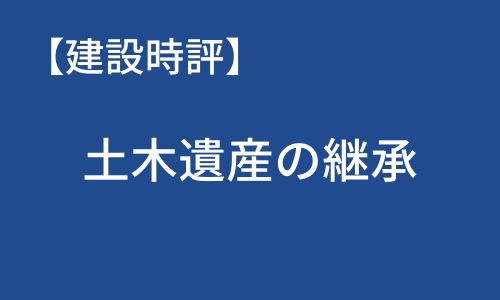
もう30年近く前のことである。北上川分流施設を改築するお手伝いをさせていただいた。戦前に行われた分水事業では、ドラマティックなエピソードを持つ信濃川の大河津分水路事業が土木マニアの間ではあまりに有名であるが、その陰に隠れている感のある北上川分流施設も、知野泰明氏の丁寧な調査(※)に依れば、土木遺産としてそれに匹敵する価値のある事業であることは間違いない。
北上川の分流施設は、宮城県の柳津町において屈曲して石巻に流れていた北上川を、新北上川として直進させ太平洋に直接つながる新流路を作り、石巻に向かう旧北上川へは2本の水路を設け、それぞれの水路に鴇波洗堰、脇谷洗堰等を設けた上で、新北上川下流部に作られた飯野川可動堰(現存せず現在は北上大堰がその役目を担う)の開閉によって分流地点の水位を変化させ、旧北上川側への分流量を制御するという壮大な治水システムであった。
石巻市街地は、江戸時代から北上川(現:旧北上川)の河口部に位置する舟運の一大拠点として、河岸ギリギリまで建物が立ち並んでいたため無堤であった。元々の分流施設もそんな石巻を守るための事業であったが、さらに治水水準を上げるために、大規模洪水時に北上川本川から旧北上川つまりは石巻市街地部側への流量をゼロとする「ゼロ分派」を行うことになった。しかし、「洗堰」はその名の通り、河川水の越流を許容する構造であるために、「ゼロ分派」を担うことはできない。さらに、鴇波洗堰も脇谷洗堰も老朽化しているため、大規模な改築が計画されたのである。
当初の分流施設改築案は旧北上川への二つの水路の間に新水路を設け、そこに新水門を設置して「ゼロ分派」を実施するというものであった。当該施設の土木遺産としての価値を全く考えなければ、非常に合理的な改築案である。
しかし、先述の知野氏の調査によって、鴇波洗堰も脇谷洗堰の土木遺産としての価値だけでなく、北上川から旧北上川への水路が2本あること自体に、当時の技術者(並川熊治郎氏ら)の叡智が詰まったシステムとして、大きな歴史的価値があることが分かっていた。その価値を踏まえて、さまざまな角度から丁寧な議論が行われ、最終的には、元々の分流システムをそのまま残し、老朽化した各洗堰は補修を行いつつ現役のまま残し、その上流側に洗堰に対して斜に構えた位置にそれぞれ二つの新水門を整備した上で、新水門は「ゼロ分派」だけを担う計画に落ち着いた。つまり、分流システムを丸ごと貴重な遺産として現役のまま保全しつつ「ゼロ分派」も新水門整備で実現するという方針である。これは当時、東北地方建設局長であった青山俊樹氏の英断により決定されたと聞いている。
この改築検討当時、筆者が一番考えていたのは、「歴史的な構造物である鴇波洗堰や脇谷洗堰をどうすれば確実に将来に継承できるか」という難題である。当初改築案では、洗堰はどちらも水無し水路に存置され、河川管理施設としての役目を終えることになる。河川管理施設ではないということは、経年劣化により補修が必要になったとき、通常の治水事業予算ではなんともならなくなることも意味している。もし重要文化財に指定されたとしても、補修費用等の金銭的な側面は、現在の文化財行政では心許ない。現役の河川管理施設であれば、補修も、そして、最悪補修もおぼつかなくなるほど老朽化した場合は撤去費用も、通常の治水事業予算で実施可能である。だから、現役として残した方がいい。そうした意見を改築案の検討の中で何度も申し上げたことを思い出す。とは言え、将来の維持管理に重い負担を残したのではないかという懸念も正直ないわけではなかった。
そして、そもそも土木構造物は、橋梁であれば道路や鉄道といった形で、人々の生活を支える使命を持ったシステムの一部を担うものである。その使命を全うするために、古い構造物が適切に更新されることも、ある意味、土木構造物としての宿命なのかもしれない。実際に適切に人々の生活を支え続けるために、多くの古き良き土木構造物が真新しいものに更新されている。そうした宿命を持つ土木構造物を土木遺産として将来に継承していくことの価値というのは一体なんなのだろうか。古き良きものをそのまま「凍結保存」していく通常の文化財とは異なる視点がもっと議論されて然るべきだと思う。
その一方で、今年5月には琵琶湖疏水の南禅寺水路閣など5ヶ所が近代土木遺産として初めて国宝に指定されることになった。本当に素晴らしく純粋に嬉しいことだと思う。しかしこれは、管理者の京都市が、国宝としてこの5ヶ所は(そして同時に指定された24ヶ所の重要文化財も含め)最小限の現況改変にとどめながら、未来永劫、維持管理し続ける覚悟を決めたということでもあるのだ。
東日本旅客鉄道が進める「TAKANAWAGATEWAY CITY」開発工事の中で、2019年から順次およそ1.3km もの延長で、ほぼ完全な形で「高輪築堤」が出土した。日本初の鉄道である新橋(汐留)-横浜間を作るにあたって、高輪付近が既成市街地であったこと、軍用地等もあって用地交渉も難しかったことから、およそ2.7km にわたって東京湾の浅瀬に築堤を施し鉄道を通したのである。その築堤こそが「高輪築堤」である。三代目歌川広重の錦絵にも、その築堤を走る列車が近代化の象徴として描かれている。土木遺産も文化財も筆者の専門ではないのだが、調べれば調べるほど、これは国宝級の土木遺産ではないかと思えてくる。
しかし、東日本旅客鉄道は開発計画を一部見直しただけで、概ね2ヶ所を現地保存する以外は大部分が「記録保存」扱いである。「記録保存」というのは調査して記録を残した上で基本的には破壊するという意味である。
一部保存するのだとしても、どうしたら自分たちの起源である土木遺産を破壊する気持ちになれるのか、その心理を筆者は全く理解できない。そもそも、東日本旅客鉄道は、日本国有鉄道が保有していた、税金によって形成された資産を継承して経営を行っている会社である。国民の資産を活用して事業を行う立場にある以上、国民共有の財産ともいえる国宝級の遺産を破棄する道理が通るのか、やはりよく分からない。正直、憤りさえ覚える。
とは言え、そんな安易な感情論では、土木遺産を残すことはできないだろう。北上分流施設の改築で筆者自身が悩み、「現役」の施設とすることで、より確かな保存継承になると考えたのとは異なり、「高輪築堤」はすでに役目を終えた施設なのである。役目を終えた施設が出土してしまったことで、ただその「保存」だけのために、維持管理費用を出し続けるというのも、もちろんおかしな話ではあるのだ。
幸か不幸か建築費の高騰によって、各地の開発・再開発事業が止まったり白紙撤回されたりしている。「TAKANAWA GATEWAYCITY」の事業計画の詳細は存じ上げないが、少なくとも建築工事単価が倍増している今しか、計画を見直すタイミングはないと思う。現役を退いた土木遺産を残す価値を再考すること、そして、それを活用して新しい価値を加えていくことはできないのか。一度立ち止まって、冷静な検討が必要であるように思う。
実はこうしたことは、「高輪築堤」に限った話ではない。土木遺産の保存継承を考えるときに、我々は、今まで文化財的な「凍結保存」を盲目的に正義と考えてきたように思う。当初の役目を終えた素敵な土木構造物があるのであれば、それに新たな役目つまり価値を付与していくことで素敵な構造物が、その面影を持ったまま継承されていくのであれば、改変したって構わないのではないか。我々はもっと柔軟な土木遺産の継承と活用を真剣に考える時期に来ているように思う。魅力ある街には必ず歴史が折り重なっている。土木構造物がその一翼を担うためにも、古き良き構造物を壊さずに済む方法をもっと模索して然るべきだと、改めて思う。
※:知野泰明「北上川分水施設の建設史と遺産的価値に関する研究 ―鴇波洗堰、脇谷洗堰を中心に―」土木学会 土木史研究論文集No.20, pp301-311, 2000
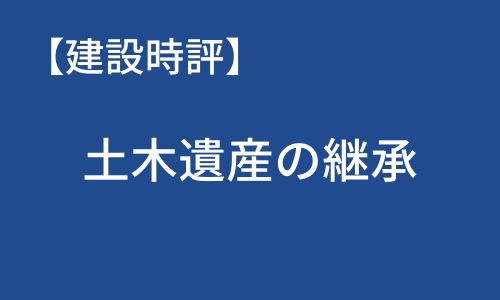
おすすめ書籍・サービス