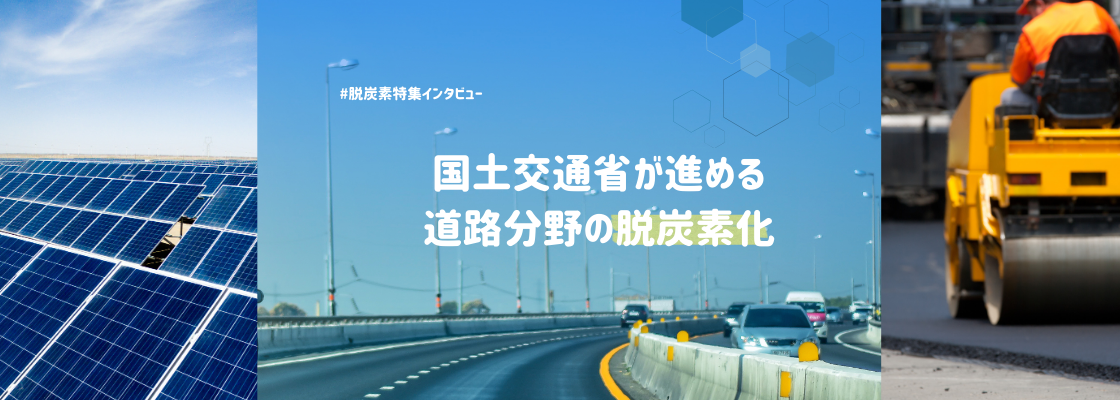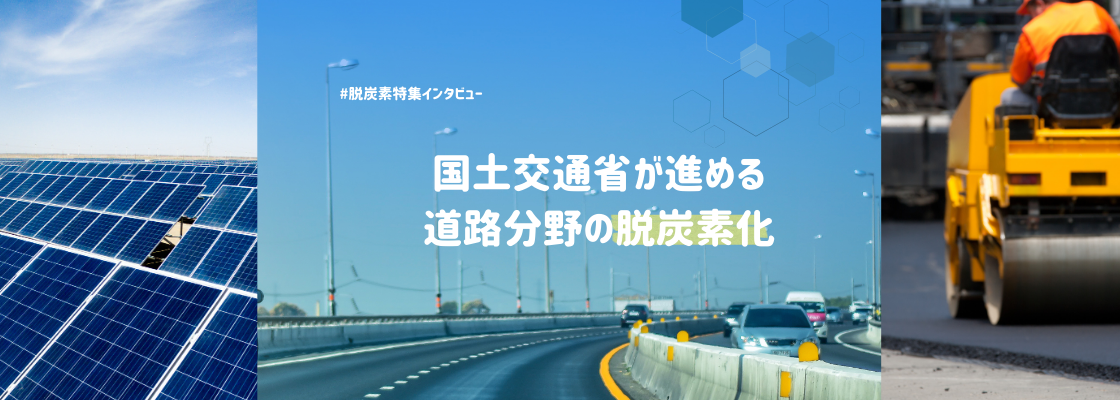
日本全体のCO2排出量約10億トンのうち約18%を道路分野が占めており、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」目標実現に向けて、道路分野における脱炭素化への取り組みが本格化してきた。
国土交通省は2024年12月に道路分野の脱炭素化推進戦略を策定し、2025年4月には道路法が改正された。
今回は道路分野の脱炭素化について、国土交通省の留守洋平氏にお話をうかがった。
■略歴
鹿児島県出身
2005.4 国土交通省 入省
2016.4-2018.6 総合政策局官民連携政策課課長補佐
2018.7-2022-6 気仙沼市副市長
2022.7-2024.7 関東地方整備局甲府河川国道事務所長
2024.7- 現職
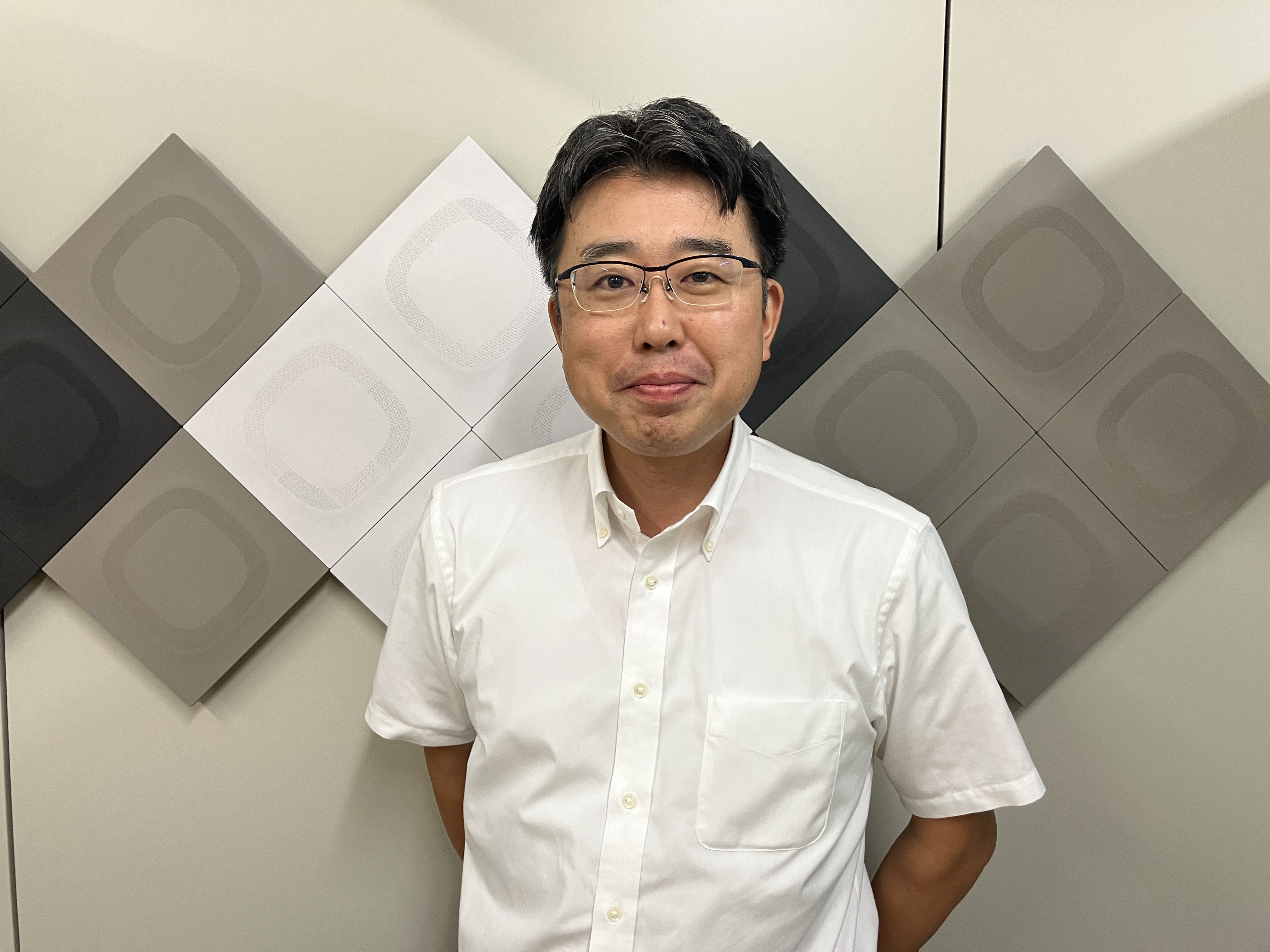
留守 洋平 調整官(以下、留守氏):
2025年は脱炭素イヤーともいえる脱炭素政策にとって重要な年となりました。
2月には地球温暖化対策計画が閣議決定され、エネルギー基本計画やGX2040ビジョンなども相次いで改訂されました。
これらの政府計画の一新を受けて、国土交通省も6月に環境行動計画を改訂しています。
政府が新たに掲げた目標に対し、道路分野でも貢献していくための施策をしっかり進めていくという新たな決意を持って取り組みを強化しています。
いままで港湾分野や航空分野では、脱炭素化の取り組みが法律に基づいて推進されていたのに対し、道路分野では体系的な取り組みは行われていませんでした。
一方で、道路分野については、道路整備、道路利用、道路管理を合わせて約1.8億t-CO2/年(2022年度)を排出し、国内総排出量の約18%を占めています。
18%という数字は決して小さくなく、政府の脱炭素化目標達成には道路分野での積極的な取り組みが不可欠です。
———そこで、国土交通省は道路分野における脱炭素化を体系的かつ戦略的に推進するための枠組みを構築。
昨年12月には脱炭素の包括的な政策「道路分野の脱炭素化政策集 Ver.1.0」が公開され、2025年4月には道路法改正が閣議決定された。
留守氏:
法改正により、道路法第1条に「脱炭素化」が明記され、第1条の2として基本理念が新設されました。
これまで明確に宣言されていなかった脱炭素化への取り組みが、法的な裏付けを持って推進されることになったのです。
道路政策全般に脱炭素化という太い幹ができたことで、今後の施策展開に明確な方向性が示されています。
新たな枠組みは、国が基本方針を示したうえで、道路管理者である国・高速道路会社・自治体がそれぞれ脱炭素化の目標設定や推進計画を策定するものです。
この計画は任意ですが、できるだけ多くの道路管理者に策定してもらうことで、全国的な取り組みの輪を広げていく方針です。
———2025年10月には道路脱炭素化基本方針が策定される予定だ。
———国土交通省では、道路分野の脱炭素化について具体的な数値目標を設定している。国直轄道路については、2030年度に2013年度比で7割削減というCO2削減目標を掲げている。
留守氏:
この目標達成に向けて、LED照明の100%導入、再生可能エネルギーの活用拡大、EV管理車両の100%導入など、11項目にわたる指標を掲げています。
これらの取り組みにより、道路管理におけるCO2排出量の大幅な削減が可能になります。
ただし、道路分野のCO2排出量の大部分は道路利用、つまり、自動車の走行によるものです。
自動車の走行によって生み出すCO2は我々の取り組みだけではゼロにできません。
ただし道路管理者としても、EV充電設備の拡充や道路空間への再生可能エネルギー設備の設置などのEV車利用促進のための環境整備を通じて「道路利用」に伴う脱炭素化に貢献していきます。
———道路分野の特徴として、全国の市町村を含む多数の道路管理者がいる。これらすべての管理者を巻き込んだ取り組みをすることで、その効果とインパクトは大きなものになると期待されている。そのため、国土交通省は、2030年に向けた協働プロジェクトを実施していく。
留守氏
「協働による2030重点プロジェクト」では、道路照明のLED化、再生可能エネルギーの活用、低炭素材料の導入促進など、6つの施策を設定しています。これらは国だけでなく、高速道路会社や地方自治体、民間企業との協働により推進される包括的な取り組みです。
道路照明のLED化は、国、高速道路会社、地方自治体がそれぞれの管理区間で取り組みを進めており、国直轄道路では2030年度に100%の切り替えを目標としています。
再生可能エネルギーの活用は、国と高速道路会社が協働して推進しています。道路管理におけるエネルギー消費の約80%は電気が占めているため、再生可能エネルギーの活用により大幅なCO2削減が可能になります。
道路空間を活用した太陽光発電設備の設置なども検討しており、エネルギーの地産地消にも貢献する取り組みです。低炭素材料の導入促進については、高速道路会社、地方自治体に加えて民間企業も重要な役割を担っています。
———道路分野の脱炭素化において、新技術の導入は重要な要素である。国土交通省が重点的に推進しているのが、低炭素アスファルト、ペロブスカイト太陽電池、走行中給電の3つの新技術である。
✔新技術①低炭素アスファルト
———従来のアスファルト製造では100℃を超える高温が必要だが、この技術により約30℃の温度低減が可能となる。
留守氏:
低炭素アスファルトは、製造時のエネルギー消費量が削減でき、CO2排出量を7%から18%程度削減できる効果が確認されています。
製造温度が低いため作業環境の改善や安全性向上にもつながります。
また、舗装後の交通開放までの時間短縮も可能で、工事による交通への影響を最小限に抑えることができます。
さらに、冬季の施工においても低温で作業できるため、品質確保の面でもメリットがあります。
———現在、全国のアスファルト混合物出荷量に占める低炭素アスファルトの割合は0.5%程度だが、国土交通省では2030年度までにこの割合を6%まで引き上げることを目標としている。
留守氏:
低炭素アスファルトの普及のために、入札時の評価制度において低炭素技術を高く評価する仕組みや総合評価方式での加点なども今後、検討が必要と考えています。
公共事業での率先使用により需要を創出し、量産効果による従来品との価格差縮小を促進することで、民間分野への普及拡大を図っていければと考えています。

—先行事例としては、東京都の取り組みがある。
留守氏:
東京都は、低炭素アスファルトの導入の先進的な取り組みを行っています。
事前審査制度を導入し、道路工事全般に低炭素アスファルトの適用を進めています。
このような自治体レベルでの積極的な取り組みが、全国的な普及のモデルケースとなっています。
・✔新技術②ペロブスカイト太陽電池
———現在、シリコン太陽電池が主流だが、さまざまなタイプの太陽電池が開発されている。その中で、日本発の次世代型太陽電池として注目を集めているのが、ペロブスカイト太陽電池である。軽量で柔軟性があり、従来の太陽光パネルでは設置が困難だった場所への設置が可能である。
留守氏:
ペロブスカイト太陽電池は、最近量産が開始されたばかりですが、日本発の新技術として政府全体で普及促進に取り組んでいます。
道路分野では、将来的に高速道路の遮音壁などへの設置が考えられます。
もし実現できれば、その延長を考慮すると大量導入による事業効果が期待できます。
現在は経済産業省と環境省が中心となって実証実験への補助金を提供し、技術の実用化を支援しています。
✔新技術③走行中給電
———ワイヤレスで自動車に充電できる設備。走行しながらの給電が可能で、EV車のバッテリー容量を小さくできることから、公道での使用が期待されている。
留守氏:
現在は、公道での設置に向けての技術実証実験の段階です。
万博会場内で実証実験が行われているほか、高速道路会社も積極的に新技術の導入を進めており、NEXCO東日本では走行中給電システムの実証実験を計画しています。
脱炭素に関連する技術は日々、進化を続け、さまざまな新技術が開発されています。
国土交通省では、これらの新技術を慎重に評価し、効果的なものを選別して導入していく方針です。
実証実験を通じて技術の有効性を確認し、全国展開に向けた基準策定を行うプロセスが重要となります。
留守氏:
道路分野の脱炭素化は、国土交通省単独で実現できるものではありません。
道路管理者、建設業界、材料メーカー、技術開発企業など、多様なステークホルダーとの連携が不可欠です。
特に数が多く、全国の市町村まで含めた幅広い道路管理者の協力が必要となります。
2025年10月の基本方針策定後には、全国の道路管理者に向けた説明会を開催し、取り組みの必要性と背景を共有していく予定です。

今後は、道路管理者の計画策定を支援するためのマニュアル整備など、小規模自治体でも取り組みやすい環境を整備していく方針です。
民間企業との連携では、新技術の情報収集や評価、実証実験の実施などの取り組みを進めていきます。
各省庁の補助金制度の活用や、入札における総合評価方式での加点など、脱炭素化に取り組むメリットを実感できる仕組みづくりを進めていきたいと考えています。
脱炭素化への取り組みは組織のCSR(社会的責任)の観点からも重要な意味を持っています。大手デベロッパーなどでは、CSRの観点から低炭素材料の使用を積極的に行い、工事に活用する動きも見られます。
このような意識の変化により、脱炭素化に取り組む組織が増えることを期待しています。
留守氏
道路分野の脱炭素化は始まったばかりです。
まもなく、道路法が施行され、道路脱炭素化基本方針が策定される予定です。
またそれに伴い、近日中には道路分野の脱炭素化政策集をバージョンアップする予定となっています。
新たな枠組みのもと、全国の道路管理者一丸となって取り組むことで、2030年目標の達成と2050年カーボンニュートラルの実現に向けた確実な歩みを進めていく所存です。
———道路分野の脱炭素化は、環境対策ではなく、インフラの老朽化、頻発化・激甚化する災害、人口減少による管理のあり方といった社会課題の解決や、未来の新たなモビリティ社会実現につながるインフラ変革でもある。