

出水 享(でみず あきら)

みんさん、こんにちは!✨
わたしは建設物価調査会のキャラクター、西園寺ルミです。「土木をなりたい職業No.1にしたい!」という強い思いで活動しているデミー博士。今回、その取り組みの一環として、九州工業大学で特別講義を行うことになりました。テーマはずばり「インフラメンテナンス」。未来の技術者を目指す学生さんたちが、グループに分かれて熱い議論と発表を繰り広げました。わたしたち建設物価調査会も、この貴重な学びの場を取材させていただきました!その様子をレポートします📸✨
出水 享(以下、デミー博士)
長崎大学の出水享氏(通称:デミー博士)が、九州工業大学の学生42名を対象に「インフラメンテナンスは必要か?」をテーマとした特別講義を行いました。対象となったのは、土木や建築を学ぶ学生たち。将来の社会基盤を担う技術者の卵たちです。講義は今回が2回目。1回目では、土木や防災をはじめとするインフラの現状や役割についてデミー博士が解説しました。そして2回目となる今回の講義では、学生が主体的に考え、議論し、発表する実践型の学びが行われました。
学生たちはまず、3週間かけてテーマを調査し、各自がパワーポイント資料を作成。7つのグループに分かれ、一人ずつ発表を行い、活発な質問や意見交換が飛び交いました。その後、議論を重ねてグループとしての意見を整理し、新たにグループ発表用の資料を作成。最後に、全体の場で各グループが発表し、再び質問と議論を交わしました。
発表、議論、意見の集約、そして再び発表へ――。この一連のサイクルこそが、デミー博士が大切にした「学びの型」であり、学生に“現場さながら”の経験を積ませる狙いが込められています。また、この講義の大きな目的は、将来、インフラ整備や維持管理の判断を行う立場になることを見据え、自分なりの意見を考え、相手にわかりやすく伝える力を養うこと にあります。
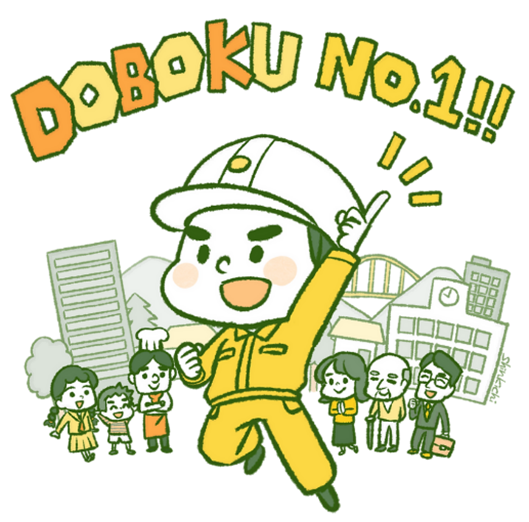
発表テーマの結論
「インフラメンテナンスは必要か?」という問いに対して、7グループすべてが「必要」と回答しました。不要とする意見は出ませんでした。
| 観点 | 主な意見 | グループ数 |
| 必要性の理由 | ・住民の安心・安全の確保 ・経済活動を支える基盤 | 7 |
| 課題 | ・老朽化インフラの増加 ・人材不足・予算不足 ・高コスト構造 | 複数 |
| 今後重要なこと | ・予防保全による長寿命化 | 7 |
| ・戦略的・計画的な更新 | 3 | |
| ・新技術の導入(効率化) | 3 | |
| ・官民連携 | 1 | |
| ・持続可能なメンテナンス | 3 |
学生たちの発表では、研究者や実務者にとっても示唆に富む考えが多く出されました。

「学生の発表から、インフラの維持管理がいかに重要かを理解できたことは素晴らしい成果です。一方で、現実には予算や人口減少の制約の中で、すべての構造物を守ることはできません。だからこそ、どこに重点を置くかを考える『選択と集中』の判断力が必要になります。
『守れないものが出てくるかもしれない』という意見も、実は非常に価値のある視点です。異なる考え方を受け止め、自分なりの優先順位やリスクを整理して伝える力は、将来の意思決定者に求められる力です。
今回のプレゼンは、単に『守るべき』と結論づけるだけでなく、現実を踏まえた多角的な視点で考える練習の場です。次回は、異なる意見や制約条件を踏まえて、自分の考えを整理し、わかりやすく伝えることに挑戦してもらいたいです。」
「インフラへの熱い想いを語るデミー博士」

この特別講義では、学生たちが主体的に考え、議論し、分析した成果が見られました。全てのグループが「インフラメンテナンスは必要」と結論づけ、課題と解決の方向性について具体的に示した点は大きな成果です。費用シミュレーションや人口動態を踏まえた更新計画といった視点は、教育的価値にとどまらず、学術研究や政策立案においても参考になるものです。未来の技術者がどのように社会基盤を支えるべきかを考える上で、本講義は重要な一歩となりました。

おすすめ書籍・サービス