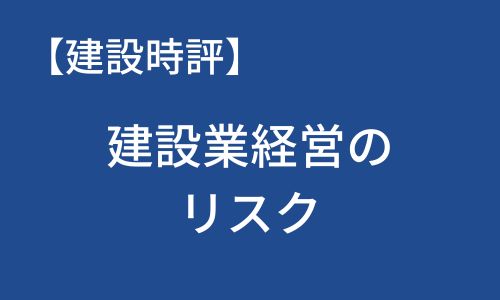
帝国データバンク(TDB)や東京商工リサーチ(TSR)は企業倒産の集計レポートを定期的に発表している。最近のそれは、倒産リスクの高い建設業の小口(負債1億円未満)倒産が多いことを伝えている。中小零細では資金繰り余力が小さいため、負債が膨らむと即倒産に至りやすいとされる。倒産の主要因として挙げられているのは、人手不足・資材価格高騰・価格転嫁困難などである。
建設業ばかりとは言えぬかも知れないが、新型コロナ禍以後、建設業が直面する事業環境は相当に変った。一つは人手不足である。具体的には職人の高齢化や若年の入職難あるいは離職によって、工期遅延や受注失注があること。もう一つは物価高である。木材・鉄骨・住設機器などの資材価格上昇をなかなか売価に反映できず、採算悪化で倒産に至るケースが建設業で多発したと分析されている。
両社の報告から建設業の情報を拾った(表、図)。表は1993年の村本建設から始まる大手建設関連企業の倒産一覧である。大手倒産事例は民事再生法や特定調停法が施行された2000年からの約10年に集中する。以後は目立つものが少なく、一見穏やかな状況が続く。また、図は2003年以降の月次の全国倒産データのまとめである。倒産件数の棒グラフは、灰色が全産業を、赤色が内数の建設業を示す。また、緑色の折れ線は建設業の件数ベースの構成比を取った。青色のそれは負債額の構成比である。件数の構成比は20%前後を推移する。建設業の倒産数は主要産業別でみると、サービス業に次ぎ、卸・小売業計と同レベルで多い。
一方、負債額の構成比はやや低めの10%強を推移するが、建設業の大型倒産があった月は跳ね上がる。図の全期間中の平均を計算すると、件数ベースが22.8%、負債額ベースが12.8%だから、建設業は冒頭に書いたように、小口倒産が多いことが裏付けられる。
この図で気掛りなのは、新型コロナ禍前の2020年頃まで月100件前後を推移していた倒産に急増の兆しがあることだ。長期でみたこの図では2000年代冬の時代はさらに多い500件ほどもあった。一般に大型倒産があると連鎖倒産が出て数が増えがちでもある。今はまだそのレベルには至らないが、過去10年でみると最多の更新が続いているとのことである。
中小建設業が倒産に至る理由を詳しく見ておきたい。倒産リスクという観点からの最近の研究の一つに高橋らの論文(文献1)がある。3年分の経審データと倒産企業情報を組み合わせて統計分析したこの論文では、倒産企業にみられる特徴を次の4つで整理した。
1)著しい低収益、
2)人材確保の不安定、
3)内部留保がなく債務超過、
4)負債に係る支払い負担が大きい状態。
より具体的に言えば、総資本に対する利益剰余金の低さや固定負債の多さ、経常利益といった収益面の低さで内部留保が困難な状態が継続、ということになる。昨今は大手の賃上げ動向が顕著で中小建設企業の動向が注目されるが、資金繰りや財務状況が改善できない中で無理な賃上げを行えば赤字になる傾向も一部でみられる。
一方、財務状態が健全に見える企業の中にも倒産例がある。流動資産が常に流動負債を上回りながら倒産した典型例では、大規模案件を慎重に検討せずに請け負った結果、一度の貸し倒れ損失が大きな打撃になったもの、また、固定資産への過剰な投資が特徴的なバランスシートの例がある。具体的には成長計画なしに設備投資を行った結果、役に立たない資産で資本を圧迫し、必要資金がなくなり破綻する場合など。高橋らの結論部分では「…倒産企業は業績や債務の利息が悪化した状態では、売り上げの回復や利益率の上昇を図ることは自力では難しく、倒産リスクを低下させることは難しかった」と結ぶ。
今年生誕100年を迎えた古川修の1963年出版のベストセラー『日本の建設業』は、筆者には今読んでも目の開かれることが多い書である。古川は「建設業の中小企業的な性質」の章で次のように書いている。「一つの企業の消滅によって二つ以上の企業の独立をみることが珍しくない。消滅企業の遺産があるとすれば無形の資産、特にのれん、ほかは少量の人的組織である。…(中略)…経営の継続をおびやかす条件は、このほか過小受注・過大受注・赤字受注・工事代金未回収などが主なものだが、これらは建設業経営がつねに当面しているものであって、特別な条件ではない。…(中略)…過大受注は中小建設業のもっともおそれるところといってよい。しかも企業規模の拡大にとっては、工事量の増大、大工事の入手が不可欠であるだけに、この危険は魅力的なものだ。工事量の増大は経営にとって必要運転資金の増加と、ときによると機械などに対する資金の固定化と、管理組織の拡大を強いる。増加した固定資産や経営組織の稼働は、拡大以後に保証されていない。」(pp.79-80)
これらは高橋らが得た結論ともよく符合することに驚く。建設業経営のリスクやそれへの対応術は、今も昔も変わらないポイントがあると思えてくる。
前出表に関して、大型倒産が近年見られない点に触れたが、その代わりにM&Aが盛んになった。直近では大成建設が任天堂創業家の資産運営会社YFO を通じ、海洋土木に強い東洋建設の買収で合意、銀行主導でない動きに注目が集まる。このほか、インフロニア・ホールディングスが三井住友建設をTOB(株式公開買い付け)で買収する等の報道がある。2023年末には大成建設がピーエス・コンストラクション(旧ピーエス三菱)を子会社化した。さらに、不動産・住宅大手による建設会社の買収・子会社化の例もある。大和ハウス工業によるフジタ(2013年)と大和小田急建設(2015年)、また、積水ハウスによる鴻池組(2015年)などが知られる。
斯様に大手の合従連衡の動きは盛んだが、地方の中堅や中小建設業はこの動向に無縁ではいられないかもしれない。人手不足、労務や資材のコスト高などの事業環境が厳しさを増す中で、他社動向をにらんだかじ取りが建設業の経営者を悩ませる時代が訪れている。
参考文献
1.高橋唯ほか「財務データを用いた分析と倒産情報のテキストマイニングによる近年の中小建設企業の事業継続におけるリスクの分析・考察」日本建築学会第40回建築生産シンポジウム論文集、2025.7、pp.9-16
2.古川修『日本の建設業』岩波新書(青版)495、1963
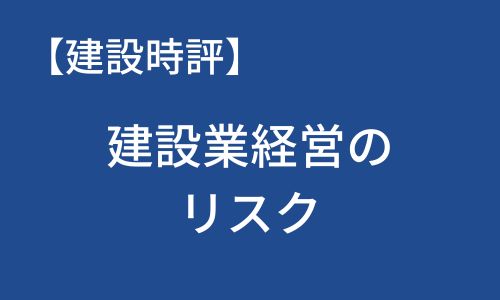
おすすめ書籍・サービス