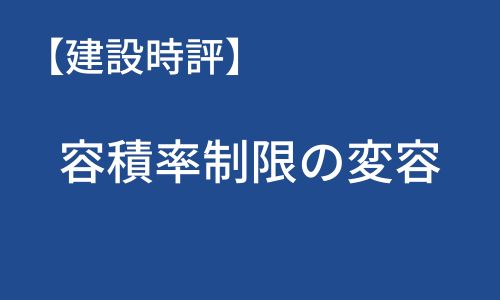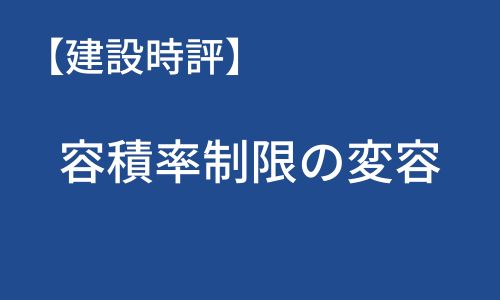
現行都市計画法は1968(昭和43)年に規律された。高度経済成長と人口、わけても都市域人口の増加によるスプロールに対応することが主眼であったが、絶対高さ制限から容積率制限へと移行したことも大きな変更であった。旧都市計画法下では、地震国の日本で高い建築物は危険と考えて、 住宅地域65尺(メートル法採用により1931(昭和6)年に20mに改正)、その他の地域は100尺(31mに改正)の絶対高さ制限を採用していた。当時の建て方で100尺はおおよそ9階に相当し、スカイラインがそろった建物が立ち並ぶ都市景観があった。
容積率制限の主旨は、建築物の規模を敷地や道路などの公共施設とのバランスの中で抑制して過密等を防ぎ、良好な市街地環境を確保することである。
2002(平成14)年の法改正で、商業地域の容積率制限について、それまでの最大1000%のうえに1100%、1200%、1300%が追加され、国土の狭い日本でも特に稀少な都心部の土地のより高度活用を可能とした。東京都が大手町、丸の内地区の一部を1300%に指定しなおしたことを受け、土地所有者は、大きな含み益を得ることとなったが、資産価値の上昇を独占することなく、エリアマネジメントや無料バスの運行などによって、利用者の利便、賑わいのあるまちづくりの増進を図り、さらなる地域価値の向上につなげている。容積率緩和を契機としてWin-Win の関係を創りだした好例である。
国土交通省は現在、容積率の特例制度として14種類を開示している¹。一定の条件を満たす場合に特例の容積率によることができる制度が経済社会の動向を背景に、次第に多くなっている。容積率の特例のなかでも際立つのは、特例容積率適用地区²である。広く都市計画の見地から容積率の上限を指定する(指定容積率)一方、複数土地所有者間の意向の一致を前提に、容積率を再指定する制度である。平たく言えば、個別の土地の容積率制限を超えて、より高度に利用したい土地所有者³と上限まで利用する必要のない土地所有者間で容積率を融通することを都市計画で認める。都市計画といいつつ、私的な土地利用を追認する制度ということができる。米国のTDR⁴に類似する仕組みで、空中権の移転などといわれる。
近年は、都市再生緊急整備地域の指定など、都市再生による活力の維持向上や国際競争力を高める手段として容積率緩和が多用される。緩和により、土地所有者の資産価値は向上する。容積率制限の主旨が、計画的で均衡のとれたまちづくりから、土地利用の多様性を求め地域活力を創出する“小槌” へと変容したといえる。
東京都では現在、隔地間の容積移転を検討している。開発が困難な斜面地や保存が望ましい緑地等を無理に宅地化して貴重な自然景観を喪失することに変えて、これらの土地の容積率を個別の制限の枠を超えて開発することも相当と思われる遠隔地の既存宅地に移転して保存と開発の並立を図る考えである。必要に応じて権利調整や対価の支払いが必要となることも想定される。いずれ、容積率という開発・利用権を個別の状況に応じてアレンジすることを公的に認めることで、土地所有者、地域・住民、都市がWin-Win-Win になるまちづくりを目指す。
容積移転の個別アレンジが可能になれば、PFI などの手法を用いるCRE(公共不動産の活用)の選択肢が広がる。岡山市出石小学校跡地利用では、廃校の跡地を定期借地権付き分譲マンション、賃貸マンション、立体駐車場、介護付き有料老人ホーム、スポーツクラブ、公共施設(市所有のコミュニティ施設、都市公園)、保育園に転換した。有機的な複合開発が評価されている。採算が重要な民間施設の供給と運営で民間活力を利用しつつ、官が実現したいサービス提供をカバーしている。
このような複合開発では、一団地の総合的設計が認められるとは限らないことがアイデアを提供する民間の隘路となる。建築基準法が規定する1敷地1建築物の原則によれば、無理やり1棟にすることが要請され、“変な建物” になる危険性がある。権利関係で見ても建物の敷地利用権が所有権、借地権、借地権の準共有、転借地権、使用借権など複雑で、未来に禍根を残さない保証がない。
複合開発では高容積率を期待する施設もあれば低容積率でよい施設もある。奇怪な意匠と権利が輻輳する建物としないためには、建物ごとに個別の敷地を有し、必要な容積率の建物を建てる枠組みを創設することである。必要に応じて土地を分割してそれぞれが独自の土地(借地権)をもつ建物を建て、容積率はそれぞれ適切なものに融通する。特例容積率適用地区制度のPFI バージョンである。爾後の維持管理についても独自の判断で、最善の選択をすることができる。
容積移転には固定資産課税も対応する必要がある。建物は延べ面積に応じて課税されることから問題は少ない。他方、土地については一般に、固定資産課税のための路線価を設定し、接道条件、形状の良否など、土地ごとの個別的要因に応じて増減価する。この際、路線価は地域全体の土地利用の程度に応じて決定するところ、都市部では容積率が大きな要因になる。要するに、建築基準法が規定する基準容積率を前提に、土地の形状等を根拠に二次元的に増減価する。他方、容積移転を受けた土地は、土地利用が地域全般から三次元的に突出するが路線価方式では原則としてこれを反映できない。
土地利用の程度が高まる容積移転先地においては実際の資産価値と比して評価額が安く、容積移転元地については評価額が高くなる。結果として、課税の公平が失われる。仮に、固定資産課税において矛盾の解決が規律できない、もしくは規律しても実効性がないのであれば、その旨を明示することが必要となる。固定資産税課税では容積移転を考慮しないことを前提に、容積移転の対価を決める際に課税の不均衡の現在価値を反映することで法(権利)と経済(価格)を均衡させることができる。
1)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/seido/kisei/kijunho.html 2025年12月14日閲覧
2)2000(平成12)年建築基準法・都市計画法改正により商業地域を適用対象として建築基準法上の特例制度として特例容積率適用区域が創設されていたものが2002(平成14)年に都市計画法の制度となり、名称も一部変更になった。
3)借地権者を含む。
4)Transferable Development Right。移転可能な開発権。